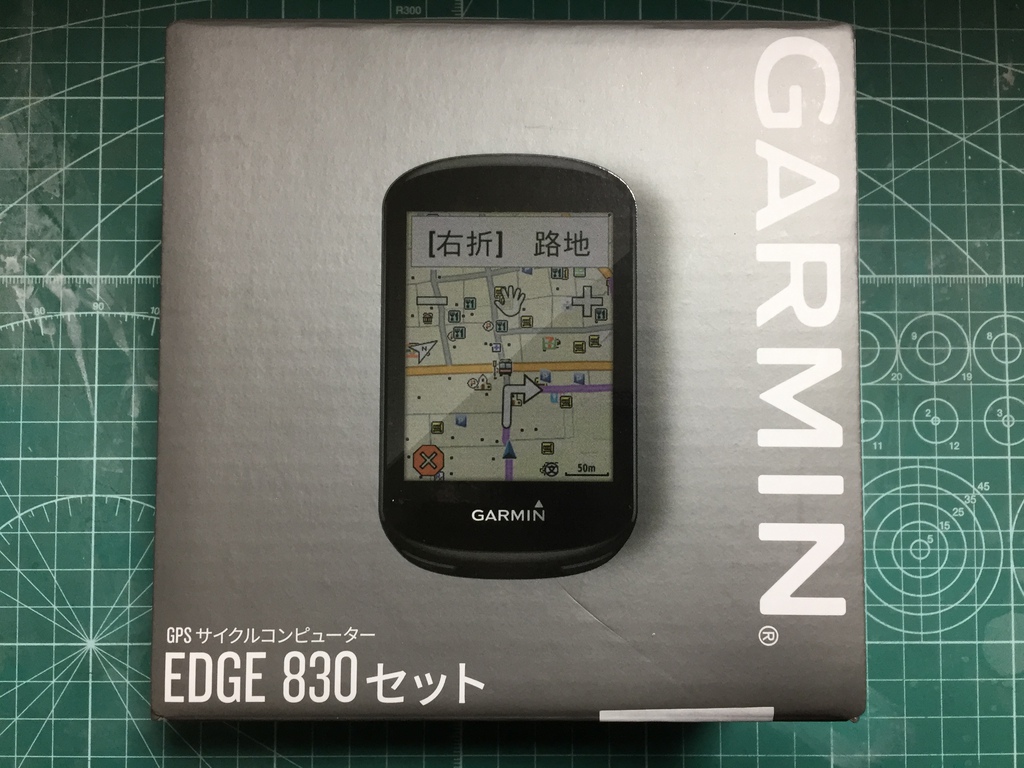今回、Wahooからリニューアル[1]されたのを機会に、初めてSPEEDPLAYのペダルを購入してみました。購入から1ヶ月、富士ヒルクライム[2]などのレース参加と合わせて、屋外を中心にしばらく実走を続けてきました。 ペダリングシステムとしては特徴的な面もあり、実走を続けてみて一長一短のある感想となりましたが、やはり他社ペダルと比較して踏み込みトルクや足首角度が意識しやすく、自身のペダリングを見直す機会になったのは最大の収穫です。今回、SPEEDPLAYで得られたペダリングの感触は、他社ペダルにも応用できそうです。 付属品 – 各社シューズに対応 ペダル本体には、各社シューズや各シューズサイズに応じた取り付けが可能なように、複数のシムや取り付けネジが付属しています。別売りの他社ペダルと違い、シムや取り付けネジを取り付けながら最適なものを選べる構成です。 シムはシューズ底面の湾曲に合わせて2種類、取り付けネジはシューズの底面の厚みに応じて長短選べます。特に今回初めての購入となるだけに、別売りで購入を躊躇するよりは、初心者には有り難い付属品の配慮です。 設定: △ (調整幅が狭い?) 今回、41EUサイズのfi’zi:kのシューズ(R1B INFINITO BOA)に取り付けましたが、ベースプレートは最初についていた青色のシムで隙間なく取り付けられました。ただし、説明書に記載があるように、シューズ底面とベースプレートに隙間がある場合には、付属の別のシムとの交換になります。 気になった点としては、ベースプレートの調整幅が狭いかも?ということです。最初に、最近主流になりつつある母指球と小指球の中間ラインにペダル軸を合わせたのですが、以下の写真にある通り、後退幅にほとんど余裕がありません。 最終的には、踏み感の違いから最大限までベースプレートを後退させるのですが、なんとか調整できたものの、シューズとの相性や、極端に深い位置のクリート位置を好む人の場合には、調整が出せないかもしれません。 着脱: △ (踏み嵌め動作が必要で緩め) 最初はベースプレートの確認をかねて、室内でステップインしてみたのですが、全然嵌まりませんでした。「馴染みがでるまで嵌めにくい」噂は聞いていたので心配しましたが、外に出ていろいろ試してみたところ、案外早くにコツを掴むことができました。金属の馴染みが必要と言うよりも、独特の装着方法を意識して慣れていく感じです。 「ダンシングして、クランクを下死点で止め、ペダルを水平して踏み抜く」動作をすれば確率高く装着できます。いまのところ「サドルに座り漕ぎながら瞬間的に踏み込んでペダルを嵌める」動作は成功率が低く、どうしてもダンシングして踏み込んで装着する頻度が高いので、若干街乗りには不向きかなと思います。 両面ペダルとは言え、SPDのようにガチャ踏みして適当に嵌まることはないので、シィティングにしろダンシングにしろ、明確に嵌めるための踏み込み動作が必要です。他社のロードペダルのように、ダンシングの必要なく、クランクを回しながら軽い動作で装着できるほうが、片面で裏返るデメリットを考慮しても、街乗りではストレスがないかもしれません。 対して、ステップアウトについては簡単で、他社ペダルと比べると、かなり軽い感触です。その反面、フローティングはかなり軽く、フローティング角度は無段階で調整できるものの、フローティング角度を狭くすると簡単に外れてしまうので、固定的な感触が好みの方には、この緩さが気になるかもしれません。 踏み感: ◯ (縦方向に安定、横方向は不安定) ペダルが小さいため、実走前はSPDペダル的な感触も想像していましたが、SPDのような点で踏むような感覚は全くなく、他社のペダルとは異なり、前後の広い面で踏んでる感触があり、独特の安定感があります。むしろ、往年のSPD-Rのような縦方向の安定感が感じられます。 ただ、仕様的にはスタックハイトは低いものの[3]、剛性感を踏まえてのダイレクト感は、シマノやLOOKのペダルより低めで、タイムのペダル的な感触でしょうか。もう少し剛性感があっても良い感じがもしますが、硬い感じはなく踏み込めるので剛性的には適切なのかもしれません。 縦方向: ◎ (安定)…
Wahoo SPEEDPLAY ZEROペダル – 1ヶ月利用してみて