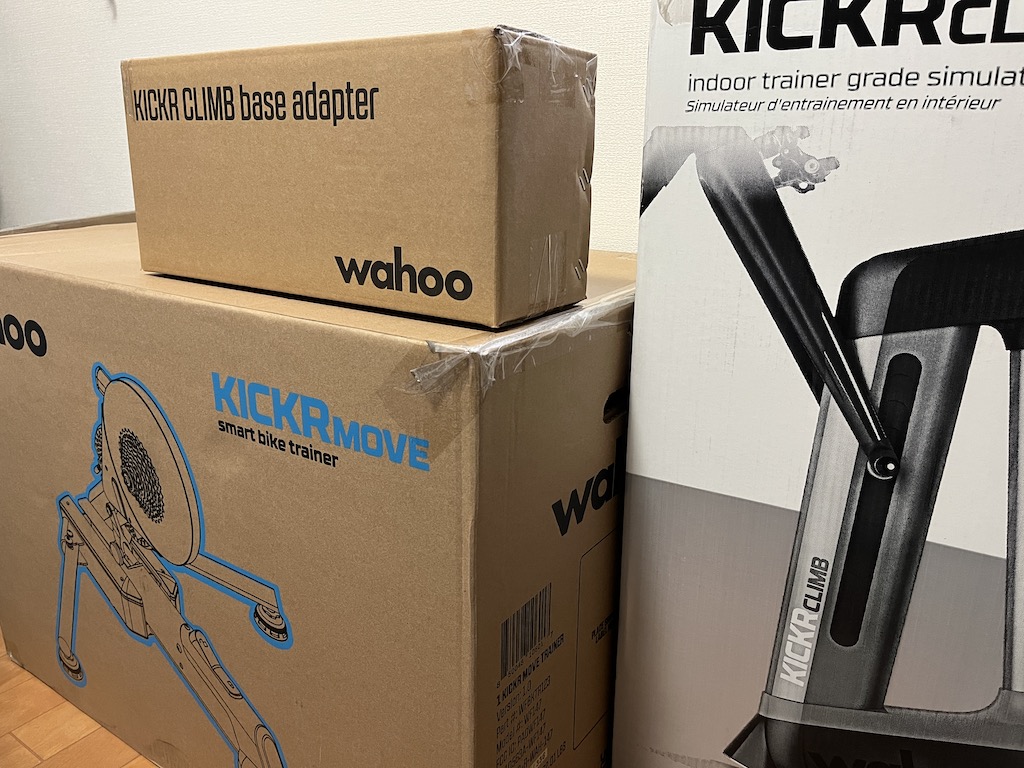先週末に行われたMt.富士ヒルクライムでの接触[1]もあり、調整も含めて、PowerTap GS + DT SWISS RR 441[2][3]のフロントホイールをメンテナンスしました。幸いにも、接触したスポークを保持していたハブやリム側への影響は見られず、スポーク交換で様子を見てみることにしました。 フロントホイールの破損確認 富士ヒルクライムで接触したホイール[1]を帰宅後、確認してみました。接触事故ながらも、幸いにも横振れは少なく、ハブやリム側への影響も少なそうです。 分解までの目視では、接触して曲がっているスポークは1本しか確認できず、全体的にテンションが抜けているスポークもありませんでした。自己責任ではありますが、接触サイドのスポークの全交換までは、必要なさそうです。 スポーク部品の注文 破損も軽微そうなので、全体的なスポーク交換まで不要[3]と判断し、今回は、まずは曲がっているスポークのみ交換して様子を見てみることにしました。交換部品の対象の、ストレートプルのCX-RAYスポークについては、パックスサイクル[4]さんで、取り寄せました。 CX-RAYスポークについては500円/本[4]と、より高価になった感はありますが、1本単位でも、国内での取り扱いがあるのは有難いところです。クリックポスト便の選択もできるため、送料も安価で済むのも助かります。 交換と調整 交換部品が届いたので、早速交換作業に入ります。まずは、曲がっているスポークを取り外して、ハブやリム側の状態を確認します。心配していた、スポークを保持していたハブフランジやリムウォール部への影響は見られず、想定通り、スポーク交換のみで済みそうです。 曲がっているスポークのテンションとニップルからスポークの出具合を確認し、新しいスポークと交換します。破損部のニップルは念のため新品に、組み立て時と同じDT Swiss製の純正ニップルに交換し組み付けます。 交換したスポークはを、交換前のニップルの出具合とテンションを目安として、一気に締め上げます。気にしていた、センターずれもなく、気になる範囲でリムの振れ取りを行い、作業完了です。 作業ついでに、後輪のホイールも確認しましたが、軽微な調整で済みました。最近のホイールは、アルミリムの剛性も高く、スポークの品質も高いためか、経年経過による緩みも少なく、調整がずいぶんと、楽になった印象があります。 最後に Mt.富士ヒルクライムでのアクシデント[1]をきっかけに、PowerTap GS + DT SWISS RR 441ホイール[2][3]のメンテナンス行いました。幸いにも、ハブやリムへの深刻な影響はなさそうで、接触したCX-RAYスポーク一本の交換で、様子を見ていくことにしました。今後も、ホイールの状態を定期的に確認し、必要に応じてメンテナンスを行っていきたいと思います。 [1] Mt.富士ヒルクライム 2025…
PowerTap GS + DT SWISS RR 441 フロントホイールメンテナンス