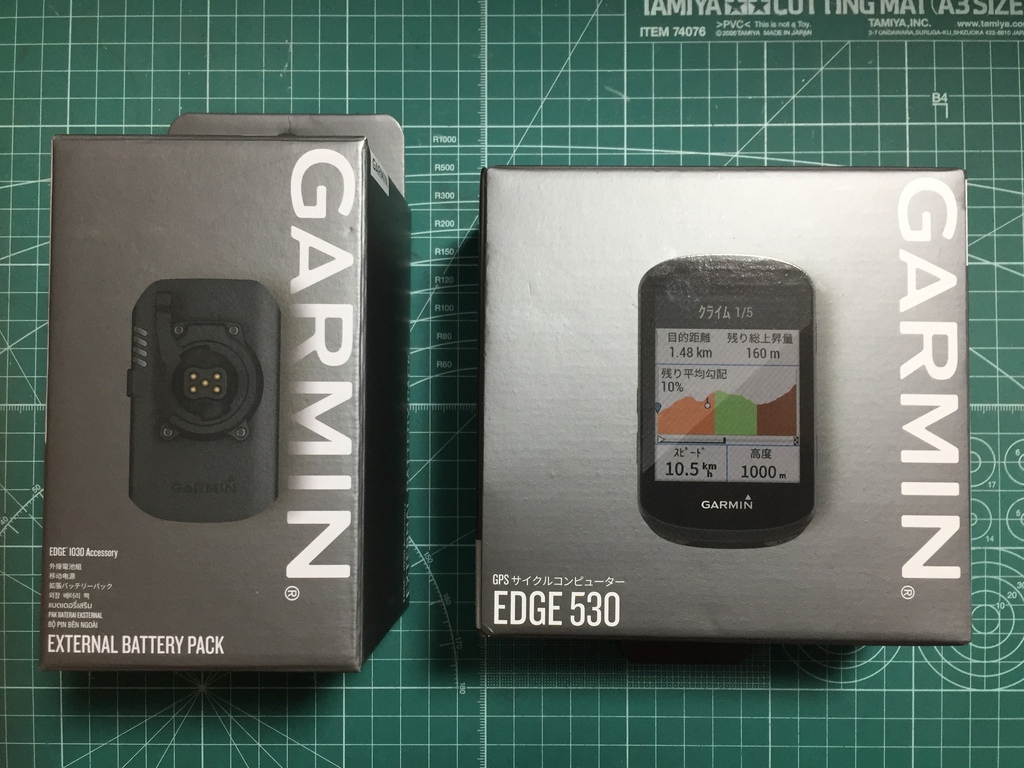2019年4月に、PowerTaps社はSRAMに買収されてしまいましたが、今回PowerTap G3が不調になったため、現在のサポート状況を含め、修理の依頼をしてみました。 結果的に、今回は交換可能なPowerCapの不調のため、修理依頼までには発展しませんでしたが、サポート窓口については現在も運営されている状況が確認できました。 故障状況 故障の状況としては、出発時には問題はなかったのですが、1時間ほどの走行中に突然パワー計測がおかしくなりました。キャリブーションを実行しても、キャリブレーションエラーが継続するような状況です。 症状としては、パワー計測が安定せず、踏み込んでいてもパワーが計測できなかったり、踏み込まなくても数値が大きく変動するような状態です。 問い合わせの結果 – PowerCapの故障 2019年4月に、PowerTaps社はSRAMに買収され、今日現在Quarq製品として販売が継続されています。ただし、販売は継続されているもの、サポート窓口は閉鎖されているのか、ホームページ上にPowerTap製品に関する問い合わせ先は見つけられませんでした。 以前、PowerTapP1が故障した際には本社窓口にて対応[1]してもらいましたが、現在は問い合わせの窓口がなく、意図的にクローズされているような状況です。 STEP1 購入販売店への連絡 無償の保証期間は過ぎてはいるものの[2]。まずは購入した海外販売店(Wiggle)にメールにて問い合わせました。すぐに、販売店側での確認が取れ、PowerTapの修理窓口となるGoogleシートのフォームを教えてもらえました。 STEP2 故障状況の連絡 販売店からの教えれもらったGoogleシートが、現在のPowerTap製品の問い合わせ窓口のようです。指定されたGoogleフォームに故障状況など記入して送信しました。 前回のPowerTapP1の問い合わせ時[1]には、基本はメールでのやり取りでしたが、だいぶ定型化されたような印象です。 STEP3 故障原因の確定 – PowerCapの不調 Googleフォームへの入力後、メールにて返信があり、PowerTapの送受信部であるPowerCapの故障が疑われるとのことでした。電池の交換しての動作確認を求められましたが、正常に動作している他のPowerTapハブのPowerCapと交換してみると、故障個体のG3は正常に動作しました。 また、今回の症状は、電池交換直後しばらくは発生せず、発生時には電池を抜き差しすることで、一時的には解消されることがわかりました。幸いにも、今回不調になったPowerCapも騙し騙し使える状態なので、しばらくは様子を見るということで、サポート窓口には連絡し、終了となりました。 結論 – しばらくは様子見 今回、PowerCapの故障が原因と判断されましたが、PowerCapは簡単に交換が可能な部品です。修理の必要なハブ周りには問題がなく一安心です。幸いにも、PowerCapは予備もありますし、今回不調になったPowerCapも騙し騙し使える状態なので、しばらくは様子を見てみようと思います。 [1] PowerTap…
PowerTap G3の修理依頼 – PowerCapの不調