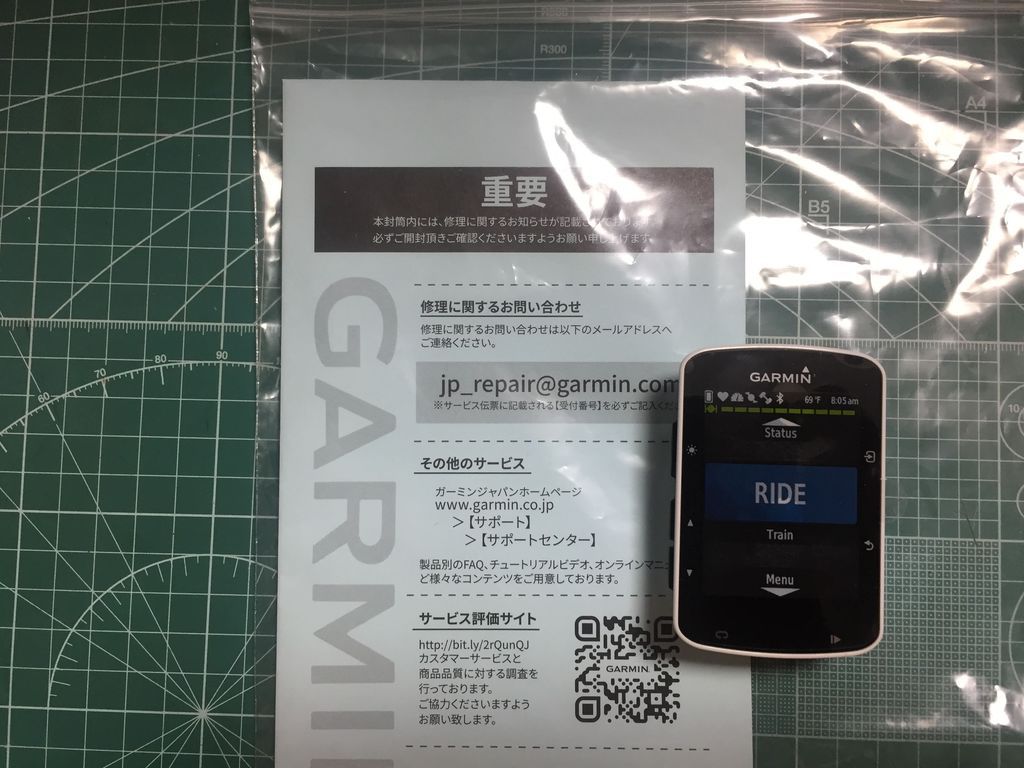チェーン交換は、自転車ではタイヤと共に頻度の高いメンテナンスで、手軽なチューンナップ方法でもあります。本来は、摩耗したチェーンからの交換となり、剛性感が復活する楽しいメンテナンスです。レースなどの大事なイベント前に、交換する人も多いと思います。 しかしながら、11速にアップグレードしてから、9速時代に感じられた新品チェーンの初期剛性が感じられず、不思議に思ってました。端的に言えば、11速チェーンでは新品と使い古しのチェーンの剛性感の違いが体感できず、チェーン交換が楽しくありません。 ふと思いつき、出荷の新品チェーンを計測してみると、シマノの11速チェーンは、同社の9速チェーンと比較しても、出荷状態の遊びが大きい(0.18% → 0.25%)ことがわかりました。おそらく、これが11速チェーンの初期剛性の劣化原因と感じています。 計測結果 9速時代は、剛性感がリフレッシュされる手軽なチューンアップとして、レース前にチェーンを交換していました。ただ、11速チェーンは交換しても、リフレッシュ感がなく、剛性感の違いが感じられず不思議に思っていました。ただし、チェーンの素材や製法自体は進化しているはずですし、耐久性的についても、実測値的にも問題はなさそうです[1]。 しばらく不思議に思っていましたが、剛性感のなさは、製法や素材よりも摩耗原因である「ローラー内径が違うのでは?」と思い立ち、手持ちのチェーンを計測してみました。比較のため計測したチェーンは、シマノ2種類のグレード(CH-HG901/CH-HG901)の11速チェーンと、9速のシマノとカンパニョーロの最上位チェーンの2種類(DURA-ACE/RECORD)です。 メーカー 型番 段数 出荷状態伸び(%) ローラー外径(mm) ピン直径(mm) Shimano CH-HG901-11 11 0.25 7.5 3.4 Shimano CH-HG601-11 11 0.25 7.5 3.4 Shimano CN-7701 9 0.18…
11速チェーンの出荷剛性(遊び)について – 9速チェーンとの比較